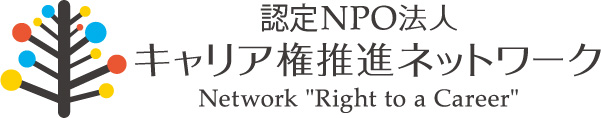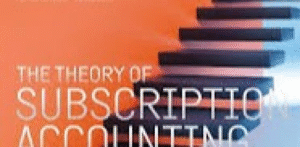先回のキャリア・ダイナミクス勉強会報告をまとめた浅野先生の論説を頂きました
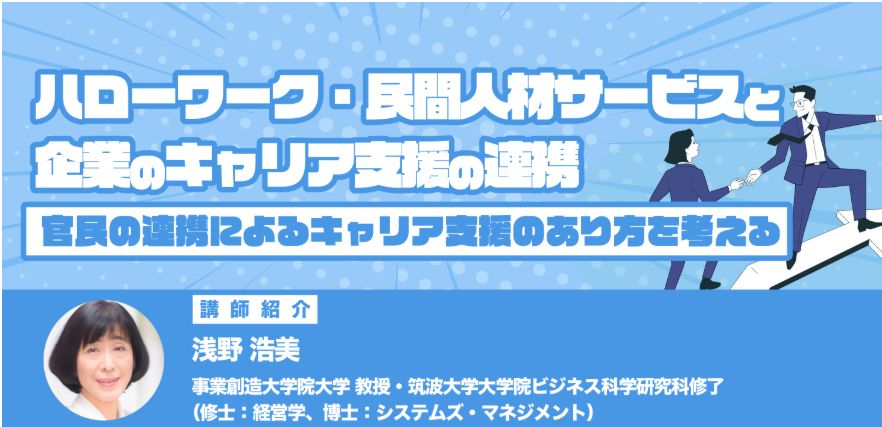
第19回「キャリア・ダイナミクス学びの場」は、10月1日にオンラインで開催されました。
https://career-oasis.jp/web/top/seminar/3731
テーマは
「ハローワーク・民間人材サービスと企業のキャリア支援の連携」-官民の連携によるキャリア支援のあり方を考える-
この勉強会の報告を、浅野 浩美 先生よりいただきました。
ハローワーク・民間人材サービスと企業のキャリア支援の連携ー官民の連携によるキャリア支援のあり方を考えるー
事業創造大学院大学 教授 浅野浩美
三位一体の労働市場改革の指針では、「キャリアは自ら選択するもの」と謳われ、
①リ・スキリングによる能力向上支援、
②職務給、ジョブ型人事の導入、
③労働移動の円滑化
を一体的に進めていくとされているが、キャリアコンサルタントにも言及されている。
厚生労働省では、2025年2月から「経済社会情勢の変化に対応したキャリアコンサルティングの実現に関する研究会」が開催され、7月4日に中間とりまとめが公表された。
内容をみると、環境変化に応じて多様な情報を活用しキャリア自律を支援する能力、企業内の労働者のキャリア自律の促進や人材育成を支援する能力が必要であり、キャリアコンサルタントの能力開発の促進、活用促進が必要だと書かれている。
私がキャリア形成支援施策を担当していた頃から、同じようなことが言われてきたが、キャリアコンサルタントの人数も増え、国を挙げて働き方やキャリアについての考え方を変えていく必要がある、とされる中で、これを実現すべき度合いは格段に高まっている。
さらに、厚生労働省は、7月7日に「今後の人材開発政策の在り方に関する研究会報告書」が取りまとめた。
これまでも、今後の人材開発政策の在り方についての検討は何度も行われてきたが、今回は、労働供給制約が誰の目に明らかになり、生成AIなどデジタル技術が進む、ある意味待ったなしという状況の中で検討されたものだという特徴がある。
報告書を見ると、多様な人材が多様なかたちで働くようになる中で、キャリアを自ら選択し、人材開発を進めていくための視点として、「個別化」、「見える化」に加えて、複数企業による人材開発である「共同・共有化」という視点が示されている。
先日、厚生労働省の令和8年度概算要求が公表されたが、キャリア形成支援に関しては、全体として、キャリア形成・リスキリング支援センター(全国47か所)、キャリア形成・リスキリング相談コーナー(全国各地のハローワーク)などで引き続き取り組みを進めていくほか、リスキリングの機運醸成のための全国キャンペーンを展開することなどが含まれている。
官民が連携していくうえでは、キャリアコンサルティングの効果を説明できることも重要である。
労働政策研究・研修機構が2025年3月に公表した報告書では、キャリアコンサルティングの効果を分析し、キャリアコンサルティングを受けた人の方が、キャリアについての満足感やワーク・エンゲイジメントが、統計的に有意に高いことを示している。
この分析では、性別、年齢などといった要因の傾向をそろえ、実験のような環境をつくり出して比較をしている。このほか、キャリアコンサルティングは役に立った、また受けたいと答えている人の割合も、それぞれ6割、5割と高いこと、キャリアコンサルティングを受けて将来のことがはっきりした、と答えた人の割合が4割を超えること、因果関係までは言えないが、キャリアコンサルティング経験がある人の方が、幅広い分野でキャリアを形成していることなども確認されている。
官民の連携を考えるうえでは、最近の企業のキャリアについての考え方を知ることも重要である。
改正内閣府令によって、2023年3月末に決算を迎えた上場企業は有価証券報告書に人的資本に関する情報を開示することとなったが、うち自由記述部分を分析したので紹介したい。
人的資本についての自由記述の文字数は企業によって相当異なる。
多いからよいということもないかもしれないが、多く書いているところは熱心だとみて、多い企業、中程度の企業、少ない企業に分けて、特徴的な語を見たところ、多い企業では、「戦略」や「キャリア」などの語が特徴的にみられ、従業員のキャリアを意識し、戦略的に取り組んでいる様子がうかがえる。
ハローワーク・民間人材サービスと企業のキャリア支援の連携という観点で、連携事例を調べてみると、現時点では、地域若者サポートステーションなど、ハローワークが登場する必要性が高い、難しい支援についてのものはあるが、それ以外のものはそれほど見られない。
企業内のことは外に出にくいということもあるが、キャリア形成・リスキリング推進事業では、ハローワークは在職者の支援を行っている。能力開発にも「共同・共有化」という視点が求められることを考えれば、今後はさまざまな連携の可能性があると考えられる。
最後に、Web労政時報で2月に1度、「キャリアコンサルティング―押さえておきたい関連情報」(https://www.rosei.jp/readers/web_limited_edition/series?series=3206)を発信している。
無料でお読みいただけるのでご覧いただけるとうれしい。
また、11月22日、23日に、日本キャリア・カウンセリング学会が30周年記念大会(https://jacc-conf.info/30th/)で、キャリア支援に関するシンポジウムなどをいくつも行う。
こちらは無料ではないが、会員以外でもOKなので、よかったら覗いてみていただきたい。